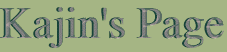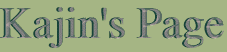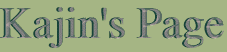

宇宙が見える。佳人の鉱物フィールドワーク'95〜'96 ̺8
超・稀産鉱物《バナジン銅鉱》採集記
愛知・岐阜県境の旅
岐阜県には「神岡鉱山」や、恵那郡蛭川村の「薬研山」など、鉱物コレクターが一度は訪れたい産地が密集している。日本列島の創世紀に想像を絶するような激しい造山活動が集中したのだろう。たとえば、我が国で最も美しいサファイヤの結晶を産出したのも、トパズの巨晶を産出したのもこの地域だった。エメラルドの鉱物名を「緑柱石」と言うが、それの子供だまし程度のものもここから産出する。さらに「ルビー」の巨大な結晶が発見されたと言う話も伝わっている。なんでも、奥飛騨の更に奥深い山の中ということらしいが、目星はついているのでいつか必ず訪れたいと思っている。だか実を言うとこれらの宝石鉱物ばごく一部を除けば、実に他愛のないものばかりで、とてもアクセサリーになるようなものではないらしい。そうは言っても、宝石の産地として遠い他国のことしか思い浮かぱない我々にとっては、こうしたものが我が国にもちやんと存在すると言うだけでも、ちょっと豊かな気持ちになってくる。
今井先生は、もし日本にもダイヤモンドが眠っているとすれば、岐阜県だろうと断言する。で、サファイヤ(鉱物名=「コランダム」。和名を「青玉」という)は、栃木県板荷でもごく稀に産出するとあって、既に2回挑戦しているのだが、それを内蔵する母岩についての知識が充分でなかったため、発見できなかった。3回目には発見できるという確信があるので、そのときは本紙で報告したい。
さて、たまたま私に、名古屋市内での講演依頼の話が舞い込んできた。こんなことでもなければ、なかなか愛知県にまで足を伸ばすチャンスはない。妻に促され、決心した。依頼者が提示してきた演題が、私の本の題名と同じ『宇宙につながった日』だったが、話の終わりを“鉱物につながった日”に持っていけばいいことだ。これで両立。岐阜県寄りの愛知県設楽町には、前から私が憧れていた「パイロクスマンガン鉱」という、マンガン鉱物を産出する、世界的に有名な鉱山が存在する。
この鉱物は普通は結晶形が判然としないピンクの塊状で産出するが、ここのものはルビーに酷似した色彩と光沢をもち、lʔ〜20ʔ程の8面体自形結晶を持っている。その大きさと美しさは他に類を見ないため、世界的に有名になった。実は私の目的の一つがこれだった。だがそれ以上の驚くべき鉱物が、愛知県には眠っていたのだ。それを「バナジン銅鉱」と言う。
「バナジン銅鉱」はレアメタル(稀元素)のバナジウムと銅が結合した鉱物で、これまで我が国ては全く発見されていなかった。それが5年前に木曾川沿いの岐阜県某所の河岸で発見された。だが、その“産地”とやらは、わずか40センチ四方。その範囲内に数個だけ産出が認められただけだった。このため、発見者による標本の採集と同時に“絶産”となり、以後採集は不可能となってしまった。この鉱物の結晶は、まさに顕傲鏡サイズで、一見、皮膜状に母岩に成長する。
色彩は、淡いグリーンを帯びた黄色、もしくは黄色。その産状は、まさに餅に生えたカビか苔の菌糸のようだから、鉱物に関心のない人の目を引くようなものではない。しかし私はすっかり魅せられてしまっていた。ものの本にも、これについては記載がなく、7月に刊行された最新の鉱物採集ガイドに、そのカラー写真が、産地名を隠したまま紹介してあるのみだ。しかも繰り返すようだが“絶産”とある。ところが事前の調査で、まだ採集できる可能性がわずかにあることが分かった。それは発見された産地とは、木曾川を挟んで対岸の愛知県の某所。その情報提供者名と産地名は、ともに極秘になっているため、残念ながら明かすことばできない。
「バナジン銅鉱」発見! 9月21日。鉱物採集の旅、いや、その日の午後7時に開催される名古屋講演に向けて、妻とともに朝8時半出発。中央高速を突っ走り、目的地には午前ll時頃に到着した。木曾川河岸の岩場に立つ。ワ二の背中のような奇岩が河岸を埋め尽くしている。そのわきを「ライン下り」の小舟が観光客を満載して下っていく。いったい、どこから探せばいいのだろう。余りの規模の大きさ、広大さに戸惑いを覚える。だが目当ては、岩の中に埋もれるように走っている、真っ黒の樹木の「化石」だ。バナジン銅鉱は、その化石の表面や内部の割れ目に結晶しているはずだ。私は引かれるようにして岩を飛び越えていく。あった!足下の岩陰の遠慮がちな窪みに目が吸い奇せられる。その窪みに、幅わずか4センチ弱、長さ20センチ足らずの黒い脈が垂直に走っている。色つや、形といい、完全に石炭そのものだ。その表面のところどころを黄色い扮をまぷしたようなものが覆っている。ルーペで確認する。微小な結晶が集まって、ミクロの住人たちの遊び場のような暖かそうなコロニーが形成されている。その周囲にはブロシャン銅鉱や孔雀石に酷似した、青や緑の鉱物が結晶していて、青鉛鉱を思わせるような鮮やかな青の斑点も飛んでいる。現場到着後、わずか7〜8分のことだった。慎重にタガネを当てる。母岩が石炭だけに、容易に取り出せそうだ。漆黒の断面が鳥の羽毛のように輝いて散乱する。へエー、ほんとうに石炭なんだ!なんでこんな所に・・?余分な傷をつけないよう、細心の注意を払いながら拾い上げる。
二隻目の船が、ことさら岸に接近してくる。満杯の観光客たちが船頭ともども、こちらを向いて大声をあげている。
「あの人たちゃあ、なんであんな所にいるんだあ?!なにしてんのかねえ・・!」
ウルサイってんだよ。なにしてようがかってだろ。そうよ、そうそう、テレビのロケなんだよ!これから岩場で濡れ場を演じるとこなんだ。ちやんとピデオカメラも持ってるしな。妻と顔を合わせて苦笑する。周囲の岩場一帯を一通り見て回る。ほかに3カ所、石炭とわずかなバナジン銅鉱が見つかった。それも広い岩場の中で、わずかに20平方M範囲内に限られていたから、採集はしないでおいた。私が採ってしまえば、今度こそほんとうに“絶産”ということになってしまうかもしれないからだ。後で聞いた話では、この標本を直接採集したコレクターは私を含めて全国で5〜6人しかいないそうだ。しかもこの産地について知っている人数もこの人たちだけに限られているため、お互いの約束事により情報は永久に封印される。こうして、おそらく私が最後のコレクターになった。
目的の半分ば達してしまっていたから、充分な余裕を持って講演会に臨む。その講演会の内容は置くとして、二次会に及んだ席で静岡から馳せ参じてくれた O夫人が面白い体験を語ってくれた。それば夢の話ですか?と念のため確認したのだが、どうもそうではないという。現実の体験だとすると余りにも奇異すぎてはばかれるのだが、鉱物にまつわる、特異な話の一環として、ぜひ読者にもご招介しておきたいと思う。
O夫人はパリに長く居住しながら、オートクチュールのデザインを手がけてきたという。その社会的地位から言っても決してアプナイ人ではないことを、本人の名誉のために言い添えておこう。
彼女の奇異な体験と言うのはなにかの拍子で、ふとしたことから「岩」の内部に入り込んでしまったというものだ。それだけでもほとんどキ印ものなのだが、その内部にば素晴らしく美しい空間があって、岩の精たちの手厚いもてなしを受けたと言う段に至っては、評価のしようもないというものだ。もちろん、これが生身の現実体験であるはずもないから、意識のある特殊な状態でのトリップとでもしておくほかはない。それが現実体験でなくても、意識に起こった現実は、本人の側からは真実なものであり、またそのことで体験の重要性がいささかも減ぜられるものではない。
l2世紀のイタリアの哲学者にして、化学の始祖として名高い大天才のヤコプ・ベーメは、ある日、ボンヤリと植物を眺めているうちに、その葉の中に入り込んでしまったと語っている。そのとき彼は、太陽の光を浴びて歓喜に打ち震えている細胞たちと一体になり、その植物全体の呼吸の流れを把握することができたと言う。私自身もかって、コーラの空き瓶に挿していた真紅のカーネーションの中に“入り込んで”しまったことがある。私の場合偶然にそうなったのではなく、意図して自分の意識を花の中にトリップさせたのだが、このとき初めて、カーネーションが仲問とコミュニケーションする場合に、どのような通信手段を使っているのかを知ることになった。この花たちは、自分の生命の流れをパラボラアンテナのように、周囲に開放していて、ありとあらゆる信号をキャッチすることができるぱかりか、みずからの生命状態を周囲に伝達することのできる独自の「言葉」さえちゃんと持っている。その言葉自体は、なんとも形容し難い透き通った、一種の衝動の形で発せられるのだか、それは相手に対して、色彩や光のイメージ、あるいはその方向性の形で伝わるため、人間はおろか、動物類や同じ植物類にも完全に理解できるメッセージとなっている。私がその花の中に入ったとき真夏だというのに、彼女の内部は静謐な涼しさに満たされていて、すこぷるご機嫌だったが、このことは彼女の生命が自己を完全にコントロールできていることを物語っていた。私はその中で、日本語ではなく、彼女たちの「言葉」によって「思考」している自分が存在するのを知った。この驚くほど奇妙な感覚は、私に一時的な言語喪矢を起こさせたほどだ。つまり、花から出てきてしばらくの間、私は本当に「日本語」を忘れてしまっていたのである。
このように、人問と植物、人間と動物、あるいは動物と植物といった異種問でのコミュニケーションは、それぞれがどんな言葉を持っていようがいまいが、言葉の有無や違いに関係なく、何の支障もなく成立すると考えていい。このようなコミュニケーションは、こちらがどのような言葉を使おうが、すべて相手の言葉に翻訳された形で伝わるのだ。たとえば私がある植物に、普通の人間に話すように「日本語」で話しかけたとしよう。すると植物はその響きを光の強さや方向、あるいは色彩の形で認識する。つまり、植物たち自身が会話する際に使用する振動に、自動的に翻訳されるのだ。同じことが人間と動物、あるいは動物と植物といった間でも成立するものだから、言葉の違いや言葉の有無は全くネックにならない。なぜこのような“自動翻訳”が成立するのかといえば、すべての生命体が「意識」を有しているからだ。それは生命に初めから備わっている「気づき」のメカニズムの全体のことである。そして生命体は、自己以外の存在と、それが何であるかに、まさに“気づく”ことかできるのである。
このコミュニケーションで、おそらく最もファンタスティックで奥深い現象は、人間が異種の生命と交流した場合に体験される。先程も述べたように植物や動物が語る言葉は、多くの場合、ちゃんと人間の言葉に翻訳された形で、あるいは人間にも分かるような形で感受されるからだ。植物の「妖精」など、そうした例の典型だ。実際にそのようなものが、そのまんまの形で実在するわけではない。植物の生命エネルギーそのものが、我々には「妖精」の形として認識できることがあるのだ。なぜそうなるのかと言えば、我々の側からすれば、交流の相手がただ光の塊のような「植物の精」であるよりも、人問と同じ恰好をしている妖精の方が、はるかに会話しやすいという原理が、交流システムそのものの中に働くからだ。それが「自動翻訳」の原理であって、このようなことは我々の都合によって起こるわけではない。だから、もし犬が花と交流するような場面があるなら、その犬は、花の中に自分と同じ犬の妖精を見るだろうし、花は犬の中に自分と同じものを感覚するだろう。同じことが人間と鉱物との間で起こったなら、どのようなことが経験されうるのだろう。その意味からも、0夫人の体験は大変示唆に富んでいる。言うまでもなく、その休験は精神的なトリップの休験だ。それが彼女の場合、植物や動物ではなく鉱物に対しておこった。「妖精」とは我々が植物の生命に共振することによって表われる我々の側の一つの認識のあり方にほかならないと述べた。もしO夫人の体験が真実だとするなら鉱物が有するエネルギーも我々には人格的な存在として認識できることを意味してる。というより、そのエネルギーと一体化できた場合には、相手を人格を有する生命のように感覚できるということだ。おそらくこのようなカラクリはすべての存在間で対話が可能になるような「対話原理」の本質をなすものだろう。ただし、そのような「対話」が可能になるためには、相手と一休化することが条件になる。対話が成立してから一体化が進行するのではなく、一体化か進行していくなかで対話が成立する。
彼女は、その中に“入り込んでしまった”。先に一体化が存在したのだ。すると、大勢の人たちが表われ、彼女をもてなしてくれる。その人たちは人間だから、普通の会話が成り立つのだ。しかし、その人間たちは実際には鉱物のエネルギーの変容形にほかならない。
これらのことは彼女の意識の世界で、別の言い方をすれば、主観のなかで起こることなのだが、このような主観が成立するためには、自分の意識と鉱物のエネルギーとが一体化するという、客観的な事実がなくてはならない。では、そんなにやすやすと“一体化”ができるものだろうか?答えは“Yes!”だ。それを可能にする第一の条件は、相手への思いやりといたわりに尽きる。この感情を馬鹿にしてはいけない。条件の二は無心に相手を見ることに尽きる。「無心」は「非心」ではない。頭のなかではさまざまな思念が駆け巡っているのだが、それらの思いにとらわれないことだ。「我を忘れて」相手をただ見統けるだけで、このことが達成される。ただ、このとき自分の意見を差し挟んではならない。自分の利益を計ってはならない。相手の出方を計算してもならない。慣れるまでば難しい訓練になるが、この姿勢に、思いやりやいたわりが加われば、我々がものを見るときの自然な習慣になる。
もし、思いやることやいたわることができないというのであれば、目の前のそれが、そこにそうして存在することの意味を考えるように努めよう。これらのことが習憤になるだけで、我々は相手の言葉でものごとを考えたり、感じたりすることもできるようになる。
地域には、神が宿る存在としてあがめられている、さまざまな植物がある。杉やヒノキやケヤキの大木などがそうだ。その生命エネルギーの強さが、我々に「天狗」や「神仙」の幻覚を引き起こす。しかもその幻覚は不思議なことに、そのエネルギ一に強く共振した者には誰にも共通して起こる。「天狗」の幻覚そのものは主観的な現象であっても、それ自体が客観的なメカニズムに起因して起こることを示しているわけだ。また、ある地域では、神が宿るとされる岩石があがめられている例もある。たいていはいかにも威圧的な巨岩だったりする。このようなものに対する崇拝がただ単に大自然への畏敬の念の表われというように考えているだけでは、人間と自然界との本当の接点は見えてこない。
最初にその大木や巨岩に畏敬の念を持った人は、そこに何かを実際に見たのだ。彼は自分に話しかけてくる岩の言葉を聞いたのかもしれない。何かを教わったのかもしれない。そしてそのようなことがあたりまえであった時代には誰もが花や石や木や水になることができたのだ。少なくとも、彼らの言葉で考え感じることができた。するとどうだろう。我々は無数の自分を自然の中に隠し持っていることにはならないか。どれもが、あなた自身なのだ。あなたはどこにも存在する。だから、固有名詞のあなたが消滅することはあっても、あなた自身は決して失われることがない。あなたはこの巨大な宇宙のなかの、悠久な中枢神経活動のブロセスそのもの、その働きの輝きそのものにほかならないから。
まだ短い時間しか経っていないが、鉱物採集を通して、私ば大変重要なことを学んだ。一言で言ってしまえぱ、我々が普通に持っている、しかしほとんど使っていない感情としての「思いやり」や「いたわり」は、超能力に勝るという事実だ。これは倫理道徳の勧めでもなければ象徴的な物言いでもない。事実そうなのだ。超能力は破壊する力も持っている。殺す力も持っている。しかし、思いやりやいたわりはそうではない。それは常に生命を維持し、保護するようにしか働かない。これらの感情を言葉にする必要はない。ステイタスにする必要はさらにない。ただ、我々が本当に宇宙と交流し、自分の生活を光にあふれたものにしたいと願うのであれば、その目的に最も叶っている自分自身の財産に、もと目を向けるぺきだと言いたいだけである。
 about Harper'sMillへもどる
about Harper'sMillへもどる
 copyright by
Harper'sMill 1996
copyright by
Harper'sMill 1996